港北区医師会の保育園医部会 研修会に登壇し、園医を務める先生方や園の先生方に向けてお話をしてきました。参加申し込みが80名、当日参加者68名と盛況であり、関心の高さがうかがえます。
(追記)2025年3月21日に事後プレスリリースも出しましたので合わせてごらんください
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000149684.html
日時 令和7年2月20日
場所: 港北区医師会会館+オンライン開催
座長: 岡本義久先生(くまのこキッズアレルギークリニック院長/港北区医師会理事)
開会/閉会の辞:中野康伸 先生(中野こどもクリニック院長/港北区医師会常任理事)
講師: 西村佑美 (小児科専門医・子どものこころ専門医・一般社団法人日本小児発達子育て支援協会代表理事)
テーマ: 発達が気になる子の保育園現場における捉え方・伸ばし方・保護者との連携
終了後アンケートからも93%がとても勉強になった、と高評価で大変うれしく思っております。
今後も地域自治体や小学校への講演も続けたいと思います。
概要
本研修会では、発達が気になる子どもの保育現場での対応方法や、保護者との連携の仕方について講演が行われた。
講師の西村医師は、小児科専門医としての知見だけでなく、発達特性を持つ子どもの母親としての経験も交えながら、エビデンスに基づいた具体的な対応策を解説した。
講演では以下のような内容が取り上げられた。
- 発達特性の捉え方: 「発達障害」という言葉ではなく、「発達特性」として捉え、その子の強みを活かす考え方が重要である。
- 行動の捉え方: 「良い・悪い」ではなく、「どのように対応すれば伸ばせるか」という視点が必要。
- 肯定的注目: 叱るのではなく、子どもの良い行動を見つけて声をかけることが重要。
- 保護者対応: 保護者に寄り添いながら、「子どもの可能性を伸ばす方法がある」というメッセージを伝える。
- 実践的なテクニック: アイコンタクトの重要性や、ペアレントトレーニングの手法について。
また、保育現場における対応だけでなく、発達特性のある子どもの未来の可能性についても触れ、AI時代において「普通でないことが価値になる」視点が重要であると説いた。
参加者データ
- 申込者数: 80名
- 参加者数: 68名(参加率 85.0%)
- アンケート回答者数: 43名(回答率 63.2%)
所属する業種:
- 保育園関係者: 32名(74.4%)
- 医療機関関係者: 9名(20.9%)
- その他: 2名(4.7%)
アンケート結果
1. 講演会の内容は期待に沿うものでしたか?
- とても勉強になった: 40名(93.0%)
- まあまあ勉強になった: 3名(7.0%)
- どちらともいえない/理解できなかった: 0名(0.0%)
2. 受診を促したり介入した方が良いと思ったお子さんはいますか?
- いる: 32名(74.4%)
- いない: 10名(23.3%)
3. 講演を聞いて「発達が気になる子の保育現場における伸ばし方・親との連携」について考え方が変わりましたか?
- 変わった: 37名(86.0%)
- 知っている内容だった: 4名(9.3%)
- 変わらなかった: 2名(4.7%)
自由記述コメント(一部抜粋)
- 「西村先生の著書を拝読していましたが、講演を通じて、親としての視点を聞けたことが心に響きました。もっと早くこの知識を知りたかったです。」(医療機関関係者)
- 「保育の実際に即した大変参考になる内容でした。今後もこのような研修を希望します。」(保育園関係者)
- 「保護者への対応について、自分が無意識にカチンとくる発言をしてしまっていたことに気づかされました。今後はポジティブな声かけを心がけたいです。」(保育園関係者)
- 「発達特性を持つ子どもだけでなく、全ての子どもにとって有効な内容でした。職員間で共有し、園全体で活用していきたいと思います。」(保育園関係者)
- 「夜間オンライン開催だったのが良かった。日中の業務があると参加しづらいので、今後もこの形式を希望します。」(保育園関係者)
- 「発達支援のエビデンスを学ぶ機会として非常に有意義でした。次回は、遊びを通じた発達支援についての講演も希望します。」(保育園関係者)
- 「子どもに関わる医療者として、親として、非常に勉強になる内容でした。発達特性をポジティブに捉えることの大切さを改めて認識しました。」(医療機関関係者)
総括
今回の研修会は、発達特性のある子どもに対する理解を深め、具体的な対応策を学ぶ貴重な機会となった。特に、 93%の参加者が「とても勉強になった」と回答 し、高評価を得た。
講演内容を実務に活かし、園全体で共有したいという意見が多く、特に 保護者対応の言葉選びや、アイコンタクトの重要性に関する学びが多かった との声が寄せられた。
また、夜間オンライン開催が好評であり、今後もこの形式の研修が望まれている。
今後の課題・要望
- より実践的な事例紹介: 実際の現場での声かけや対応方法をさらに深掘りして学びたい。
- 遊びを活用した発達支援: ESDMやジャスパーなど、遊びを通じた支援について知りたい。
- 継続的な学習機会: 研修の継続開催を希望する声が多数。
結論:
研修会は 大変有意義な学びの場となり、多くの参加者が今後の実践に活かしたいと考えている ことが明らかとなった。今後も、このテーマに関するさらなる研修の開催が期待される。
アンケート結果はコチラからもご確認いだけます。

講演内容詳細
発達特性の理解
- 近年、発達障害という言葉は「神経発達症」と呼ばれるようになり、よりニュートラルな表現へと変化している。
- 発達特性は「治すべき障害」ではなく、「活かすべき個性」として捉えられるべきであり、特性の理解が最優先。
- 2013年のDSM-5改定、2022年のICD-11改定により、診断名の変化が進んでいる。
発達特性のある子の支援
- 言葉の遅れや行動の違いは、必ずしも知的障害を意味しない。
- 公立小学校1年生の約12%が「何らかの支援が必要」とされており、認識の広まりが進んでいる。
- AI時代において「普通でないこと」が強みになる。独自の視点や創造性は、AIにはない価値を持つ。
発達特性のある子どもを伸ばす方法
- 肯定的な関わり方が重要であり、特に「褒める」ことが効果的。
- 褒め方の4つのパターン
- 感心する(「すごいね」「さすがだね」)
- 励ます(「その調子!」)
- 感謝する(「ありがとう」)
- 関心を示す(ナレーション:「靴を履いてるね」「ご飯を食べてるね」)
- 褒め方の4つのパターン
- 子どもの行動を 「増やしたい行動」「減らしたい行動」「やめさせたい行動」 に分類し、適切な対応を行う。
- 対応の工夫
- 「無視・待つ・ほめる」の原則を活用し、感情的に叱るのではなく落ち着いた対応を心がける。
- 「C.C.Q.」テクニック(Calm: 穏やかに、Close: 近づいて、Quiet: 落ち着いた声で話す)を活用する。
保護者との連携
- 保護者の心理として、以下のような傾向がある。
- 「ポジティブなアドバイスがほしい」
- 「情報は集めているが、曖昧な言葉は不安」
- 「優しい励ましより、現実的な目標がほしい」
- 「診断よりも、今どうすればいいか知りたい」
- 保護者に対する伝え方の工夫
- 例: 「この子は伸びるタイプですね」「好奇心旺盛ですね」「学者タイプですね」
- 「診断は最優先ではなく、困りごとの対応が大事」と伝えることで、保護者が前向きに取り組みやすくなる。
- 保護者から相談があった際、小児科への受診も一つの選択肢。ただし、小児科医の対応には個人差があるため、適切な相談先を案内することが大切。
質疑応答
- Q: 年長児が発達の気になる子の行動を止めようとしたとき、大人はどう声をかけるべきか?
A: すぐに注意するのではなく、「なぜこの行動をしているのか?」を考え、一緒に接し方を学ぶことが重要。 - Q: 保護者から相談があった際、小児科を勧めてもいいか?
A: 小児科の対応には差があるため、発達相談に詳しい先生を選ぶことが望ましい。
まとめ
- 発達特性のある子どもを支援するためには、まず 「認識のアップデート」 が必要。
- 保育現場では、特性のある子どもへの 「肯定的な注目」 を増やすことが重要。
- 保護者への対応では、 「ポジティブな視点」 を伝えることで、前向きな関わりを促すことができる。
- 就学前の6年間は、子どもの発達において最も重要な時期。この期間に適切な支援を行うことが、その後の人生を大きく左右する。






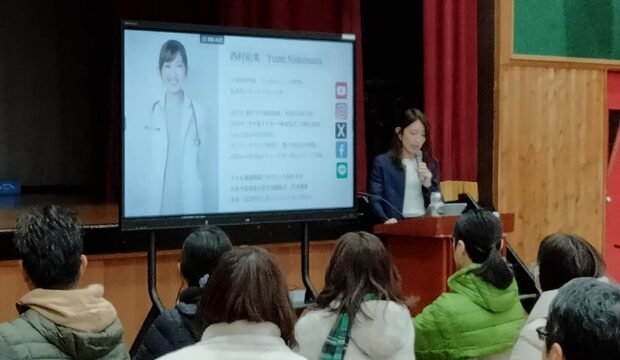

コメント